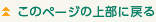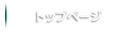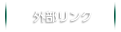2013年2月18日(第2632回例会)
(担当会員:清水 美溥 君)
世界の主要国の指導者が揃って交代した「動乱の年」2012年。続く2013年は、動乱の幕がいよいよあがる年と言ってよいでしょう。日本、中国、インド、ロシア極東部がじしめく「アジア半球」はいまや世界経済の推進エンジンとなっていますが、同時に東アジアの強国が凌ぎを削る新たなグレート・ゲームが戦われる地域でもあります。
そうした動乱の幕開けを告げるように、北朝鮮は、2006年、09年に続いて、12年暮に長距離ミサイルの発射実験を強行し、今回もまた国際社会の反対を押し切って核実験に手を染めました。アメリカのオバマ大統領は、今度の北朝鮮の核実験を「真の脅威」と表現して国連決議を取りまとめるべく中国を懸命に説得しました。長距離ミサイルの射程が伸び、日本や韓国だけでなく、アメリカ本土にも届く水準に達しつつあることをこう表現したのでしょう。確かにミサイルに装着する核弾頭も小型化、高性能化しています。
アメリカ政府の対応は遅きに失したと言うべきです。自国の直接の脅威にならないとして、これまで十年にわたった中東での「ブッシュの戦争」に持てる力のすべてを注いでしまった結果、中国や北朝鮮がある東アジアに巨大な戦略上の空白を生じさせてしまったのです。その隙を衝いて中国や北朝鮮は、攻勢に出ています。戦略上の真空地帯ほど恐ろしいものはありません。周囲から乱気流が流れ込み天下大乱のきっかけになるからです。
こうした情勢を読み解いて、国家の舵取りを試みるには、適確な情報戦略が欠かせません。「インテリジェンス」の感覚を存分に磨いておかなければいけないのです。「インテリジェンス」とは、指導者が下す決断の拠り所となる情報のエッセンスです。ここでいう指導者とは国家のリーダーに限りません。会社や家庭の舵取りを委ねられている人々にも当てはまります。膨大で雑多な一般情報、つまりインフォメーションの海の中から、心眼を凝らして、真贋を見極め、情報の本質を紡ぎ出していく。その過程で得られる最後の一滴が「インテリジェンス」なのです。経営者の方々は、そうしたインテリジェンスに依拠し、会社の命運を賭けて決断をしているわけです。しかし日本では、「インフォメーション」と「インテリジェンス」を区別する適切な訳語がなく、いずれも「情報」と訳されます。しかしながら「インフォメーション」と「インテリジェンス」は似て非なるものです。ホワイトハウスでは、政府部内の情報機関が国益というプリズムを通して、膨大な「インフォメーション」から「インテリジェンス」を選り分けて精製し、大統領に毎日届けています。一方日本では、この両者を自身で選りわけなければいけない。そこには、日米のインテリジェンスの文化の違いが歴然です。日本の政治リーダーは、国家の運命を担って、日々「インテリジェンス」に接し、国家の針路を定める事にあまりに関わってこなかったのです。半世紀にわたって、日米同盟のシニアなパートナーである米国に、大切な「インテリジェンス」を安易に委ねてきたことは否めません。
「インテリジェンスに同盟なし」という有名な箴言があります。米国は自国の国益に沿って情報活動をしているのであり、他国の為に自国の人材と資金をつぎ込んでいる訳ではありません。自国の針路を自力で定めるには、独自の「インテリジェンス」が必要です。様々なノイズを除いて、貴重なシグナルを聞きとり、その上で国家の舵取りをしていかなければいけません。日本は先進国8カ国の中では唯一対外的な情報機関を持っていません。情報なき経済大国ニッポン。それを戦後の米国が望んでいたのでしょう。これまではそれで済んだのかもしれません。しかし米国がかざす傘は破れかかっています。過去半世紀にわたって機能してきた日米同盟のシステムは、今後半世紀にわたって機能するとは限りません。
国家だけでなく民間の組織でも、本来、新鮮な情報を全身にいきわたらせるための情報の心臓にあたる「インテリジェンス・サイクル」を本来備えています。この情報の回路を粛々と回すことで、組織のリーダーは誤りなき決断を下すことが可能となります。しかし、2011年3月11日の運命の瞬間、管官邸にはこの「インテリジェンス・サイクル」が機能していませんでした。かくして惨事は深刻な様相を呈していったのです。福島第一原発が大地震と大津波に襲われ、そのまま手を拱いていれば、やがて炉心の核燃料物質がメルトダウンを起こしてしまうことは明らかでした。適確な「インテリジェンス」がリーダーに提供されていれば、原子炉を廃炉にする覚悟で大胆な手を打たなければいけなかった。しかし現実には、危機のリーダーたる菅直人総理は、何の決断も下そうとしませんでした。そればかりか、総理は苛立ち、あろうことか、翌12日の早朝には官邸のヘリコプターを駆って現地に飛び出していきました。ここでも、何らの決断も下さず、悲劇の様相は一層深まっていったのです。
ちょうど同じ頃、米国のホワイトハウスには、米国にとっての10年の敵、オサマ・ビン・ラディンがパキスタンの首都から50キロほどの軍事都市アボターバードの邸宅に潜んでいるという重大な「インテリジェンス」が飛び込んできていました。これをきっかけに「インテリジェンス・サイクル」が唸りをあげて回り始めました。そして軍の作戦当局は、武力発動に踏み切るか否か、大統領の最終決断を促したのでした。作戦命令書を一晩家に持ち帰った大統領は、決断するは我にありと、作戦命令所に署名をしたのです。これを受けて、ビン・ラディン捕捉作戦は発動されていきました。作戦の成功率は高くても70%。完璧な「インテリジェンス」など存在しないのです。
「今後の国際政治はアジアが担う」。クリントン国務長官はこう断言して、21世紀を太平洋の世紀と捉えて、環太平洋・アジア重視の外交・安全保障を打ち出しました。TPP・環太平洋経済連携協定は、ヒト・モノ・カネの行き来を自由にする貿易の枠組みですが、外交・安全保障政策が背景にあります。オバマ政権はTPPを最優先課題に掲げており、対中戦略でアメリカの協力を仰ぐ日本は、TPPに参加しない選択肢などないと言っていい。アメリカが主導するTPPには若干の例外が透けて見えます。つまりアメリカは「聖域なき関税撤廃」などそもそも主張していません。安倍政権はこれを国内の説得材料にTPPへ参加する腹づもりなのでしょう。同時に民主党政権で亀裂が入った日米同盟を再建して対中戦略で日米が共同歩調をとることが安倍新政権に課せられた責務です。
![大阪西ロータリークラブ [ 国際ロータリークラブ第2660地区 ]](http://www.osaka-westrc.org/wp-content/themes/osakawestrc/common/img/logo.png)